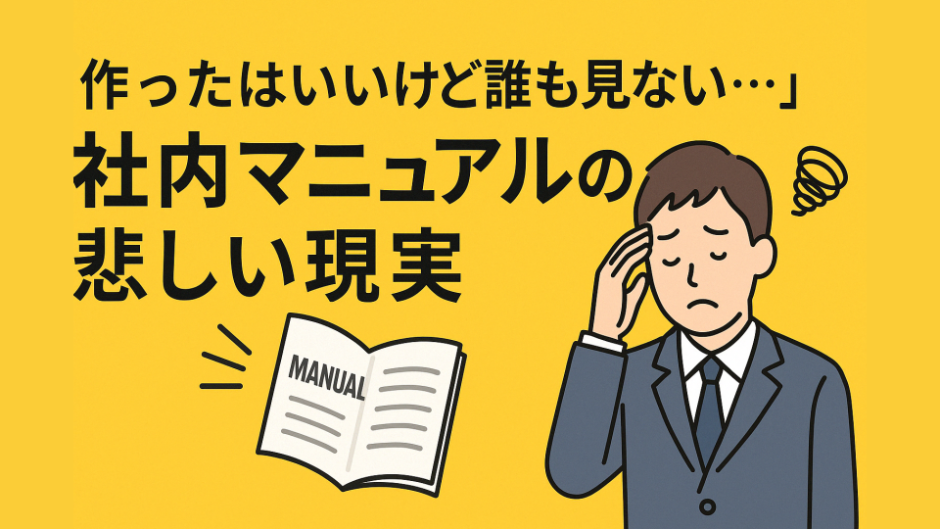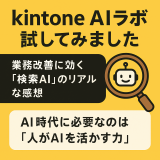「作ったはいいけど誰も見ない…」社内マニュアルの悲しい現実
最近は人材の確保が難しい状況でみなさん悩まれていると思います。
せっかく採用できた新入社員に、効率よく業務を覚えてもらうために必要なのが「社内マニュアル」。でも、こんな経験はありませんか?
- 去年の研修資料を見てみたら、すでに使っていないシステムの説明が…
- 業務プロセスが変わったのに、マニュアルはそのまま…
- 「このマニュアルどこにあったっけ?」と探し回る時間が無駄に…
- 結局、先輩社員に直接聞いた方が早いと思われている…
多くの中小企業では、一度作成したマニュアルやドキュメントが更新されないまま放置され、新入社員教育の度に「今年も資料を作り直さなきゃ」という状況が繰り返されています。
なぜマニュアルは活用されないのか?その3つの理由
1. アクセスのしにくさ
共有フォルダの奥深くに保存されていたり、どこにあるのか社員が把握していなかったりと、「見たい時にすぐ見られない」環境になっています。業務中に必要な情報をサッと確認できなければ、結局は「人に聞く」という行動パターンが定着してしまいます。
2. 更新の手間
業務プロセスは日々変化しているのに、マニュアルの更新は後回しになりがち。「誰が」「いつ」「どのように」更新するのか、明確なルールがないことが多いのです。
3. 魅力的なコンテンツ不足
長文のテキストだけのマニュアルは読みづらく、理解しにくいもの。特に若い世代の社員は、視覚的にわかりやすい情報を求める傾向があります。
kintoneで実現する「生きるマニュアル」システム
kintoneは業務を行うクラウドシステムです。そのkintoneアプリの操作方法や業務の流れ、社内ルールなどが見える場所にあれば良いですよね。日々の業務で使用するシステムの中に必要な情報があることで、自然と社員の目に触れる機会が増え、活用される可能性も高まります。
このような課題を解決するために、私たちはkintoneを活用した「マニュアル運用機能」を開発しました。なぜkintoneなのでしょうか?
業務改善が加速する
「Manulet(マニュレット)」は、kintone上でマニュアル運用を驚くほどシンプルにするツールです。複雑だったマニュアル作成や管理が直感的な操作で誰でも簡単に行え、業務改善を加速させます。
現場での使いやすさを徹底的に追求し、情報共有のスピードを劇的に向上。従来のマニュアル運用を次のステージへ導く新しい解決策です。
kintoneのメリット
- アクセスしやすい環境: 普段の業務で使うkintoneの中にマニュアルがあれば、わざわざ別のシステムや場所に移動する必要がありません
- 更新履歴の管理: 誰がいつ何を更新したのか、履歴が自動的に残るため、最新情報の把握が容易です
- 通知機能: マニュアルが更新されたら関係者に自動通知することで、常に最新情報を共有できます
- 検索性の高さ: 必要な情報をキーワードで素早く検索できるため、大量のマニュアルの中から必要な情報だけを取り出せます
- マルチメディア対応: テキストだけでなく、画像や動画、図表なども組み込めるため、視覚的にわかりやすい資料が作成できます
導入事例:A社の場合
製造業のA社では、以前は紙のマニュアルとイントラネット上のPDFファイルで業務手順を管理していました。しかし、kintoneのマニュアル運用機能を導入したことで、次のような変化が生まれました:
- 検索時間の削減: 必要な情報を探す時間が平均15分から2分に短縮
- 問い合わせ減少: 先輩社員への質問が30%減少し、本来の業務に集中できるように
- 更新頻度の向上: 月1回程度だった更新が週1回程度に増加
- 新人研修の効率化: 入社後の基本業務習得期間が平均2週間短縮
A社の総務部長は次のように話します:「以前は新人が入るたびに資料を作り直していましたが、今はkintoneの中で常に最新情報を維持できるようになりました。何より、社員が自発的にマニュアルを見るようになったのが大きな変化です」
kintoneでマニュアル運用を始める3ステップ
Step 1: 現状のマニュアルを整理する
まずは既存のマニュアルを洗い出し、必要なものと不要なものを仕分けしましょう。社内の業務プロセスを可視化し、どのような情報が必要かを明確にします。
Step 2: kintoneアプリの設計
マニュアルの種類や部門ごとにカテゴリを設定し、検索しやすい構造を設計します。更新頻度の高い情報と低い情報を分けて管理することも効果的です。
Step 3: 運用ルールの策定
- 誰が更新権限を持つのか
- どのようなタイミングで更新するのか
- どのように社内に通知するのか
こうしたルールを明確にすることで、継続的な運用が可能になります。
マニュアルが”生きる文書”になるための秘訣
マニュアルを単なる「一度きりしか見ないもの」から「常に活用される生きた文書」に変えるためには、次のポイントを意識しましょう:
1. 実際の業務フローに沿った設計を
マニュアルは理想論ではなく、実際の業務の流れに沿ったものにすることが大切です。現場の声を聞き、本当に必要な情報を盛り込みましょう。
2. 定期的なレビューの仕組みを
半年に一度など、定期的にマニュアルの内容をレビューする機会を設けましょう。業務プロセスの変更や改善点を反映させることで、常に最新の状態を保ちます。
3. 視覚的にわかりやすく
長文の説明よりも、図解やフローチャート、スクリーンショットなどを活用し、視覚的に理解しやすい内容にしましょう。必要に応じて動画マニュアルも効果的です。
4. 成功事例や失敗事例も盛り込む
単なる手順書ではなく、「このようにすると成功した」「ここで失敗しがちなので注意」といった実践的な情報も含めることで、より価値のある内容になります。
マニュアルは”使われてこそ”価値がある
社内マニュアルは、作ることが目的ではなく、「活用されること」で初めて価値を生み出します。kintoneを活用したマニュアル運用は、以下のメリットをもたらします:
- 最新情報への容易なアクセス
- 業務効率の向上
- 社員のストレス軽減
- 知識の共有と蓄積
- 新人教育の効率化
新入社員が増える季節だからこそ、今一度マニュアルの在り方を見直してみませんか?「一度きりしか見ないもの」から「常に活用される生きた情報源」へ。それがkintoneで実現できるのです。
今すぐできるアクション
- 現在の社内マニュアルの利用状況を調査してみましょう
- どの業務プロセスが最もマニュアル化が必要か、優先順位をつけてみましょう
- kintoneのマニュアル運用機能についての無料相談会を活用してみましょう
業務改善は一朝一夕では実現しませんが、一歩ずつ着実に進めることで、必ず成果は表れます。
このブログ記事が少しでもお役に立ちましたら、ぜひシェアをお願いします。また、kintoneを活用した業務改善についてのご相談も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
 Gibbons
Gibbons