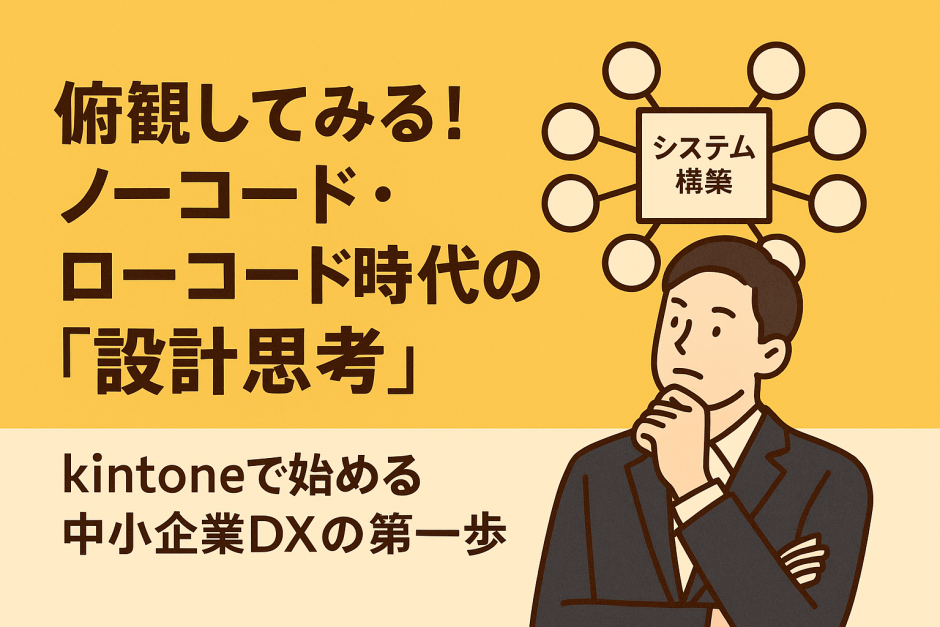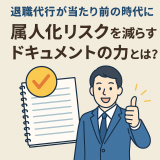中小企業の現場では今、多くの業務が「なんとなくExcelで回っている」「紙が減らない」「情報共有に時間がかかる」といった課題に直面しています。とくに営業現場では、在庫状況の把握や受注情報のリアルタイム共有がうまくいかず、顧客対応のスピードに差が出てしまうことも。
こうした業務の非効率を改善しようと、ノーコード・ローコードツールを導入する企業が増えています。中でも注目されているのが、柔軟性と拡張性を兼ね備えた【kintone(キントーン)】です。
しかしここで注意すべき落とし穴があります。
「便利そうだから作ってみた」では、かえって業務が混乱することもあるのです。
よくある課題:気づかぬうちに「非効率の再現」をしていませんか?
まずは多くの中小企業で見られる典型的な課題を整理してみましょう。
- 在庫情報がExcelと紙に分かれていて、確認に手間がかかる
- お客様ごとの対応履歴がバラバラに管理され、フォロー漏れが起こる
- 見積・受注・発注の流れが1本の線でつながっていない
- 情報が属人化しており、担当者が休むと業務が止まってしまう
こうした状況を改善しようと、いきなりツールを触り始める方も多いのですが、それは「家を建てるのに、いきなりキッチンから作り始める」ようなもの。
業務全体を俯瞰した設計がなければ、機能同士がちぐはぐになり、逆に手間が増えるリスクすらあります。
システム構築の鍵は「俯瞰」と「構造化」
まずは業務全体を“地図化”する
業務改善の第一歩は、「自社の業務を全体としてどう捉えるか」にあります。
おすすめは、以下のような可視化手法です。
- マインドマップ:業務の流れやつながりを放射状に整理
- マンダラート:課題ごとにアイディアを広げ、要素を明確に
- 業務フロー図:情報の流れとステップを時系列で可視化
ここで意識すべきは、**“何を、誰が、いつ、どう使うか”**という視点です。
これがないと、「誰のためのアプリかわからない」システムになりがちです。
kintoneによる構築:部屋割りから始めよう
kintoneでの業務構築は、住宅の設計と似ています。
✦ 全体構造(業務) → 各部屋(アプリ) → つながる動線(ルックアップ・プロセス管理)
例えば営業業務では、以下のような構成が考えられます。
| 業務機能 | kintone構成例 |
|---|---|
| 顧客管理 | 顧客台帳アプリ |
| 見積・受注管理 | 見積アプリ+受注アプリ(プロセス連携) |
| 商品・在庫 | 商品マスタ+在庫管理アプリ |
| 営業報告 | 活動報告アプリ |
そして、これらのアプリをルックアップ(連携)やプロセス管理でつなげることで、「一貫性のある業務システム」が実現します。
成功事例:設計から始めた企業の声
事例:営業スタッフ20名の工業部品商社(従業員45名)
課題:
- 見積作成に時間がかかり、在庫確認も二度手間
- 紙ベースの営業報告で管理が煩雑
対応:
- 顧客・商品・営業報告・見積・受注の5アプリを設計段階でフロー化
- 見積から受注までを一気通貫に
- 在庫データをリアルタイムで確認可能に
効果:
- 月80件以上の見積業務が3割短縮
- 営業報告の手間を年間480時間削減
- 管理者からの「状況確認メール」がほぼゼロに
よくある障壁とその乗り越え方
| 障壁 | 解決策 |
|---|---|
| どこから手をつければいいかわからない | 業務の棚卸し→図にする→関係性を考える |
| システム構築が属人化する | フロー図を全員で共有し、「見える化」する |
| 完璧を目指して動けなくなる | まずは1業務から始めて、徐々に広げていく |
| 作って終わりになりがち | 定期的に見直し・フィードバックのサイクル導入 |
次のステップ:あなたの「業務の家」を描いてみよう
ノーコード・ローコードの時代は、「作ること自体」は簡単になりました。
しかしだからこそ、「設計」こそが重要です。
まずは紙とペン、あるいは付箋やマインドマップツールでも構いません。
あなたの会社の業務全体を、一枚の絵にしてみてください。
あなたの業務の“間取り図”が描けたとき、kintoneは最も効果的に動き出します。
まとめ:業務効率化の第一歩は“絵を描くこと”から
- ノーコードツールも、「設計」がなければ逆効果になりかねない
- kintoneはアプリを「部屋」として考えると設計しやすい
- 業務を図解・構造化してから構築に取り組むべき
- 設計思考こそ、中小企業DXの成否を分ける鍵になる
あなたも今日から、業務の「俯瞰設計」を始めてみませんか?
まずはホワイトボードでも手帳でも構いません。
「この業務、そもそもどうつながっていたっけ?」と問いかけながら、図に描き出すところからスタートしてみましょう。
どの業務から「間取り図」を描いてみたいですか?
 Gibbons
Gibbons