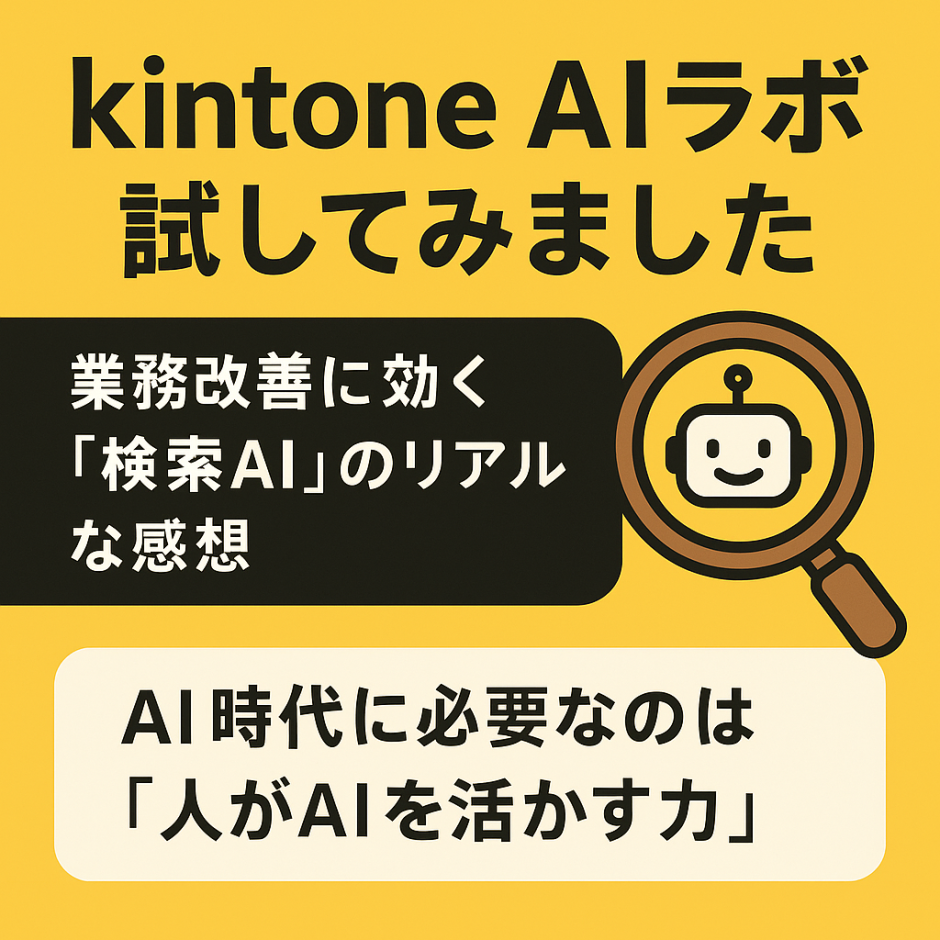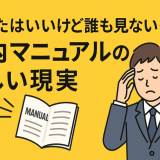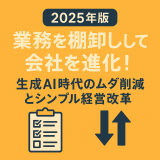AIは業務の「相棒」になれるのか?
最近、多くの中小企業で「業務の属人化をどう防ぐか?」「新人教育の効率をどう上げるか?」という声をよく聞きます。その解決策として注目されているのが、AIによる業務支援ツール。
今回ご紹介するのは、サイボウズがリリースした「kintone AIラボ」。
特にその中でも、「検索AI(旧アシスタントAI)」を実際に使ってみた体験を元に、「本当に業務で使えるのか?」をリアルにレポートします。
kintone × AIが生む新しい業務のカタチ
「検索AI」とは?
「検索AI」は、kintoneに蓄積された社内データを元に自然なチャットで質問に答えてくれるAIツールです。
技術的には、RAG(Retrieval-Augmented Generation)という手法で、あらかじめ登録されたドキュメントやレコードの中から関連情報を抽出し、それを元に応答を生成します。
つまり「AIが勝手に妄想しないよう、手元の事実に基づいて答える」――業務現場においてこれは非常に重要なポイントです。
実際に使ってみた所感
導入後すぐに使ってみましたが、第一印象は「おとなしいAIだな」という感じ。
ChatGPTのように自由に会話を展開するAIとは違い、「余計なことは言わない、間違っても言わない」という印象です。
これは、おそらくハルシネーション(AIの事実誤認)を防ぐための制御が効いているのでしょう。
ただしその反面、kintone上に十分な情報が登録されていないと、回答が薄くなるという欠点も感じました。
実際に弊社の事例でも、きちんと情報整理されたアプリがある場合はスムーズに回答されるものの、情報が曖昧なアプリだと「関連情報が見つかりません」と返されるケースがありました。
使いどころは「マニュアル×AI」かも?
「検索AI」の本領が発揮されるのは、社内マニュアルや業務ドキュメントとの連携です。
例えば弊社が開発・提供している「manulet(マニュレット)」のようなマニュアルアプリがあれば、AIがその情報を元に即答してくれます。
新人が「この作業ってどこからやるんだっけ?」と聞いた時に、検索AIが即座にマニュアルから手順を回答してくれれば、教育の手間もミスも削減できます。
弱点は「データの質と量」
逆に言えば、きちんと情報が整理されていない状態で使うと、検索AIの真価は発揮されません。
これは人に例えるなら、「資料が整ってない新入社員に何でも聞いている状態」に近いかもしれません。
AIは万能ではなく、あくまで「社内ナレッジを活かすためのツール」なのだと実感しました。
AI時代に必要なのは「人がAIを活かす力」
「検索AI」は、情報が整っていれば十分に役立つ可能性を秘めたツールです。
ただし魔法の杖ではありません。
情報を見える化・構造化してAIに渡すという前提があって初めて、業務の味方になるのです。
このことからも、いま改めて注目したいのが「マニュアルの整備」「ルールの明文化」「標準化」の3点。
AIに業務を教えたければ、まずは自分たちが「わかる形」で仕事を整えることが、最も効果的なAI活用法です。
業務をAIと一緒に進化させてみませんか?
今回ご紹介した「検索AI」はまだ発展途上ですが、中小企業の現場にこそ必要なツールになり得ます。
これからも継続的に検証していきたいと思いますので、興味のある方はぜひ【シェア】をお願いします!
また、manuletやkintoneの活用で業務改善を考えている方は、お気軽にお問い合わせください。
一緒に、AI時代の“次の一歩”を踏み出してみませんか?
業務改善が加速する
「Manulet(マニュレット)」は、kintone上でマニュアル運用を驚くほどシンプルにするツールです。複雑だったマニュアル作成や管理が直感的な操作で誰でも簡単に行え、業務改善を加速させます。
現場での使いやすさを徹底的に追求し、情報共有のスピードを劇的に向上。従来のマニュアル運用を次のステージへ導く新しい解決策です。
 Gibbons
Gibbons