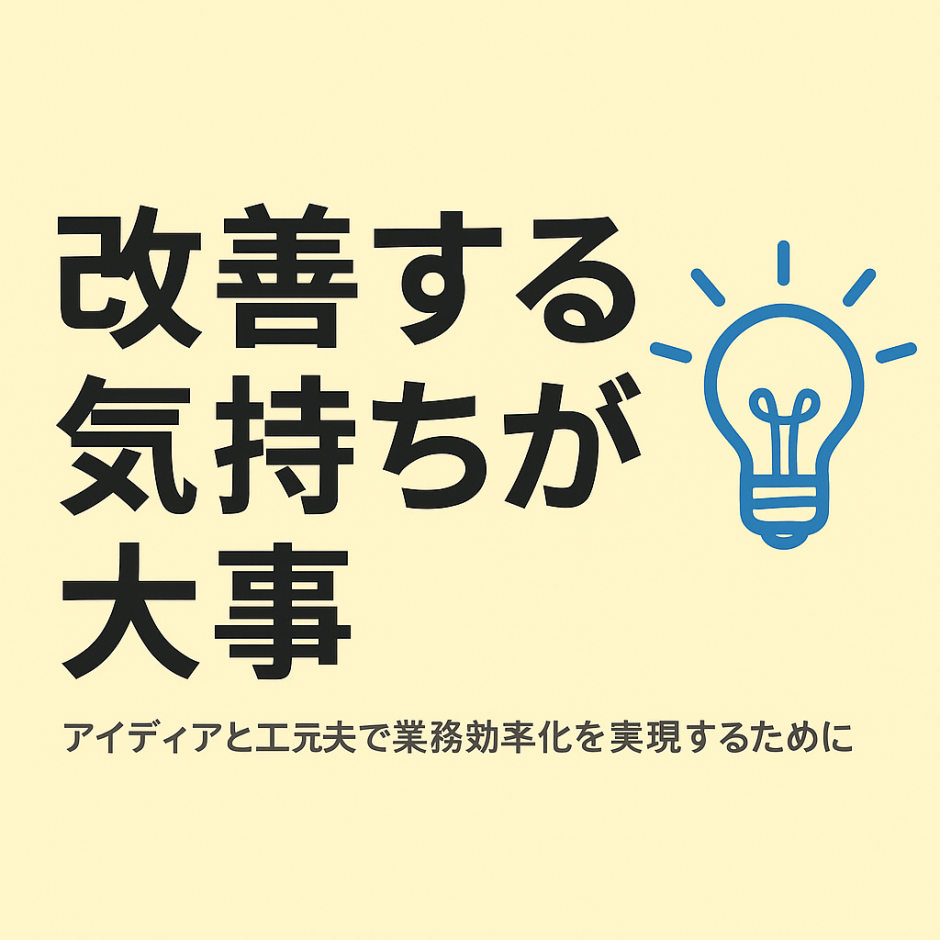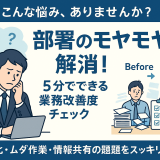~アイディアと工夫で業務効率化を実現するために~
「仕組みよりも気持ちが先」って、どういうこと?
「業務改善のためにツールを導入したい」「DXに取り組みたい」。
多くの中小企業で聞かれるこの言葉の裏側には、「なんとかしたいけど、何から手をつけたらいいか分からない」という本音が隠れています。
私たちはこれまで、さまざまな企業や自治体でkintoneを活用した業務改善の研修を行ってきました。
そこで感じるのは――業務改善がうまくいく会社には、必ず“改善する気持ち”があるということ。
ツールの使い方も大切ですが、まずは「今より良くしたい」という小さな気持ちが芽生えること。
その気持ちをどうやって育てていくのか?この記事ではそのための視点や方法をお伝えします。
なぜ、業務改善は難しいのか?
課題の背景:日常に埋もれてしまう“問題”
業務改善が進まない理由の一つは、**「今のやり方に慣れてしまっている」**ことにあります。
- 書類のやり取りが何枚も重複しているのに、それが「当たり前」になっている
- Excelで管理していた在庫が合わないのに、修正のためのルールを作らないまま続けている
- 同じ質問を新人に何度もされるのに、マニュアルを作る暇がない
これらの“モヤモヤ”は、気づかないうちに日常に埋もれてしまい、「なんとなく疲れる職場」を生み出してしまいます。
視点を変えるだけで、変化は始まる
研修の中では、こんな問いかけをよくします。
- 「今、何が面倒くさいと感じていますか?」
- 「こんなふうにできたらいいのに、と思うことはありますか?」
- 「今日からひとつだけ変えられるとしたら、どこを変えますか?」
こうした問いをきっかけに、参加者の目の前にある業務の「見直しポイント」が浮かび上がってきます。
改善の第一歩は、課題に“気づくこと”なのです。
kintoneという道具の良さ
kintoneは、業務アプリを自分たちで作れるクラウドサービスです。特別なプログラミングの知識がなくても、
・チェックリスト
・進捗管理
・申請フロー
・マニュアル管理 などをノーコードで構築できます。
kintoneで得られるビジネス効果(一例)
- 申請業務を紙→kintoneに移行し、年間200時間の削減(建設業・従業員30名)
- チャットでは追いきれなかった案件を「見える化」し、問い合わせ対応時間を半分に(サービス業・従業員45名)
こうした効果は、kintoneそのものの性能というよりも、「こんなふうにしたい」というアイディアから始まっています。
よくある障壁とその乗り越え方
よくある課題
- 「ツールが苦手な人がいて前に進まない」
- 「全体像を描ける人がいない」
- 「誰が主導するのか不明確」
乗り越え方
- 全員で改善に関わる雰囲気をつくる
→ まずは“目次”だけでも業務を分解してみる。 - 最初から完璧を目指さない
→ 最小単位の改善から始め、後から改善を重ねていく。 - ツールの使い方ではなく、活かし方を話す
→ 「何を作るか」ではなく「どう良くしたいか」を軸に話す。
実践ステップ|最初の一歩は“話してみる”こと
以下の流れを基本に研修や導入支援を行っています。
- 課題の棚卸し
現場の「面倒だな」を集めてみる - 理想の状態を描く
「こうなったら良いのに」と話してみる - 最小限のアプリを作って試す
kintoneでプロトタイプを作成 - 使ってみて、改善を重ねる
利用者の声を聞いて手直し
結局、何よりも「改善する気持ち」が原点
研修での一番の成果は、「ツールが使えるようになったこと」ではなく、「これから何かを良くしていこう」という気持ちが芽生えたことです。
ツールはあくまで手段です。
アイディアと工夫を積み重ねていくために必要なのは、「今のままで良いのか?」と問い続ける視点です。
まずは、こんな行動から始めてみませんか?
- 月に一度、「面倒だった作業」を共有する時間をつくる
- 「今日ひとつ、改善できたこと」を社内で話す
- 部署横断で「もっとこうなったら良いのに」を出し合ってみる
ツールを入れる前に、まずは気持ちのスイッチをONにしましょう。
そこからすべてが始まります。
 Gibbons
Gibbons