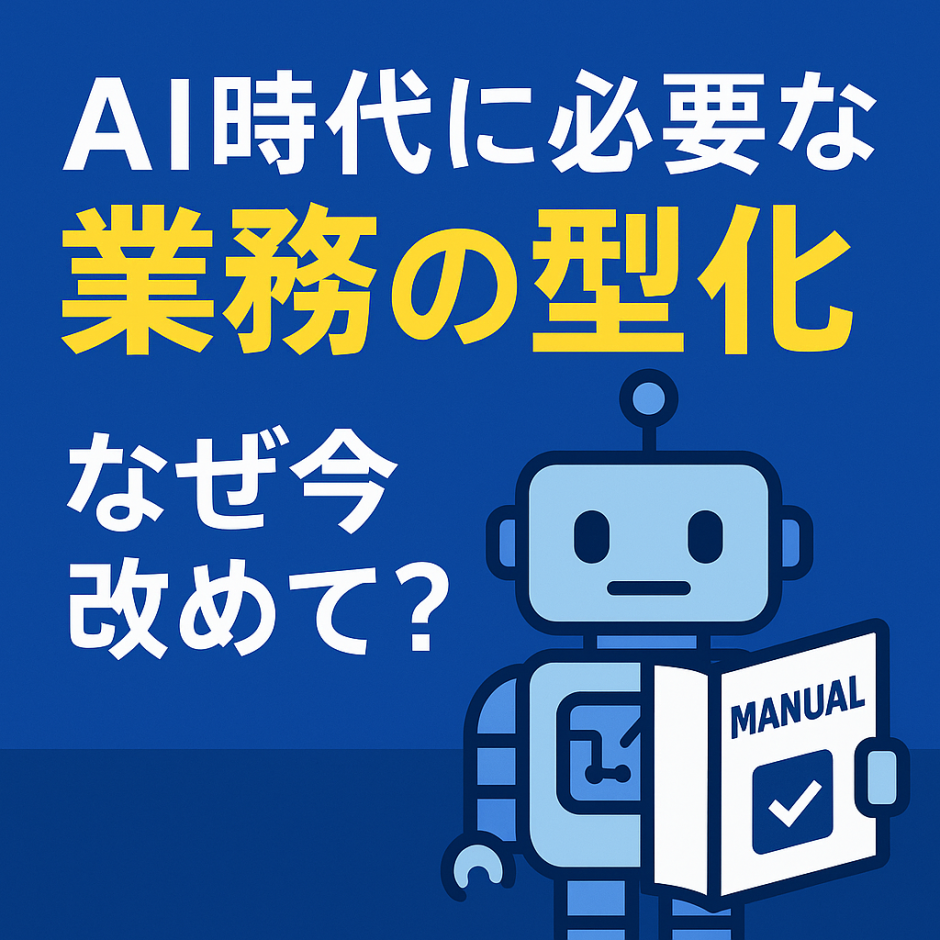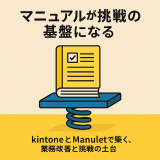「AIがすべての答えを教えてくれる時代」そんな言葉を耳にする機会が増えました。ChatGPTのような生成AIは、私たちの仕事を劇的に変えつつあります。資料作成、アイデア出し、翻訳…。まるで万能のパートナーのように感じますよね。
しかし、本当にAIがすべてを解決してくれるのでしょうか?
中小企業の経営者・リーダーの皆さまの中には、「AIを導入したけれど、いまいち使いこなせていない」「社内の業務がバラバラで、AI以前の問題だ」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。その感覚は、とても鋭いと思います。
私は、AIはあくまで「強力なツール」の一つだと考えています。そして、どんなに優れたツールも、使いこなすための「土台」がなければ宝の持ち腐れになってしまいます。その「土台」こそが、AI時代だからこそ見直すべき「業務の型化(マニュアル化)」なのです。
なぜ今、改めて「業務の型化」が必要なのか?
AIの登場で、マニュアルはもう古いものだと思われがちです。しかし、実はその逆です。AIを効果的に活用するためには、業務を「型化」することが不可欠になってきています。
1. AIは「何もないところ」からは何も生み出せない
AIは、入力された情報をもとに、新しいものを生み出すことは得意です。しかし、それはあくまで「人間が与えた情報」がベースになります。
例えば、「新しいキャッチコピーを考えて」とAIに依頼したとします。ただ漠然と指示を出すだけでは、汎用的な答えしか返ってきません。しかし、「ターゲットは40代女性、高級感がありつつも親しみやすいブランドイメージで、製品の特長は〇〇です」のように、具体的な業務の「型」を伝えることで、AIはより的確なアウトプットを生成できます。
社内の業務が属人化し、「〇〇さんの仕事は、〇〇さんしか分からない」という状態では、AIにどんな指示を出せばいいのかすら見当がつきません。AIを使いこなすためには、まず業務の「型」を明確にし、AIが理解できる言葉で指示を与える必要があるのです。
2. AI活用は、業務の標準化から始まる
「うちの会社はAIを導入したいけど、何から手をつければいいのか分からない」というご相談をよくいただきます。多くの場合、その原因は業務がバラバラで標準化されていないことにあります。
AIは、効率化や自動化を目的として導入されることが多いですが、そのためにはまず「業務が一定の流れに沿って行われている」という前提が不可欠です。
例えば、経費精算業務を考えてみましょう。 AさんはレシートをExcelに入力、Bさんは紙に手書き、Cさんはスマホアプリで…というように、人によってやり方がバラバラだと、AIに自動化を任せることはできません。 まず、「経費精算は必ずこのフォーマットで行う」という型を作り、それを社内で共有すること。AIは、その型に沿って入力されたデータを自動で集計したり、申請・承認プロセスを自動化したりすることができます。
業務を標準化することは、AI活用への第一歩なのです。
AIを活用して、マニュアル作成の手間を劇的に削減する
「マニュアル作成は時間がかかる」「専門的な知識が必要だ」といった理由で、マニュアル化を諦めている企業は少なくありません。しかし、AIの力を借りれば、この課題は大きく改善されます。
生成AIに業務内容や目的、手順の概要を教え込むことで、マニュアルの「叩き台」を短時間で作成できます。たとえば、「新入社員向けの経費精算マニュアルを作成して」と依頼するだけで、大まかな構成や文章を生成してくれます。
もちろん、AIが生成したものが完璧なマニュアルになるわけではありません。しかし、そこからが重要です。実際に業務をよく知る担当者が、生成された内容をチェックし、自社のルールや実態に合わせてブラッシュアップする。このプロセスを経ることで、ゼロからすべてを書き出すよりも、はるかに少ない労力で、質の高いマニュアルが完成します。
AIは、マニュアル作成における「最初の面倒な一歩」を代わりに踏み出してくれる強力なアシスタントです。このAIアシスタントを効果的に活用するためにも、やはり「この業務を誰にでもわかるように説明する」という、業務の「型」を意識することが不可欠になります。
AIに業務を教え込むためには、私たち人間がその業務をきちんと理解し、論理的に説明できる状態になっていなければなりません。AIを活用したマニュアル作成は、結果的に業務内容の再確認と整理を促す良い機会にもなるのです。
このように、AI時代におけるマニュアル戦略は、「マニュアルを捨てる」のではなく、「AIを使いこなしてより良いマニュアルを効率的に作る」ことへと進化しています。
業務の「型」を記録・共有する最適なツール「kintone」と「manulet」
では、どのようにして業務の「型」を記録し、社内で共有すればいいのでしょうか?
そこで私が強く推奨しているのが、kintone(キントーン)とmanulet(マニュレット)という2つのツールを組み合わせる方法です。
kintone:業務の「型」を動かす土台
kintoneは、業務アプリを誰でも簡単に作成できるクラウドサービスです。 業務の流れや情報を「アプリ」として作り、チームで共有することで、業務を「型化」することができます。
例えば、次のような業務アプリを作成することで、業務を「型化」できます。
- 顧客管理アプリ: 誰がどの顧客と、いつ、どんなやり取りをしたのかを全員が把握できる
- 営業報告アプリ: 営業担当者が同じフォーマットで日報を提出し、進捗状況をリアルタイムで共有できる
- 問い合わせ管理アプリ: 顧客からの問い合わせ内容と対応状況を全員が確認でき、対応漏れを防ぐ
これらのアプリを使うことで、「この業務はこう進める」という型が自然と定着し、業務のバラつきがなくなっていきます。
manulet:業務の「型」を記録するマニュアル作成ツール
manuletは、業務手順を簡単に作成・共有できるマニュアル作成ツールです。 手軽にマニュアルを作成し、社内で簡単に共有できるのが特長です。「紙のマニュアルは古くなるから…」「マニュアル作成が面倒で後回しになってしまう…」といった課題を解決できます。
manuletで作成したマニュアルをkintoneのアプリと連携させれば、「kintoneで業務の型を動かし、manuletでその手順を記録する」という理想的なサイクルが生まれます。 新入社員はkintoneのアプリを開き、業務を進めながら、manuletで作成された手順書で迷うことなく作業を進められる。担当者が変わっても、業務の引き継ぎがスムーズになる。
こうして業務が型化・可視化されることで、AIが活用できるデータが蓄積され、より高度な業務改善へと繋がっていくのです。
小さな一歩から始める「業務改善」のススメ
「業務の型化」と聞くと、大がかりなプロジェクトのように感じるかもしれませんが、決してそんなことはありません。まずは、以下の簡単なステップから始めてみましょう。
- 最も属人化している業務を一つ決める: 「この人がいないと回らない」という業務はありませんか?例えば、「特定の担当者しかできない請求書発行業務」や「特定の担当者しか知らない顧客情報」などです。
- その業務の「型」を言語化してみる: 誰が、いつ、何を、どのように行っているのかを、紙でもいいので書き出してみましょう。
- kintoneでその業務アプリを作ってみる: 書き出した業務の流れを、kintoneのフォームに落とし込んでみましょう。
- manuletで手順を記録する: 実際にkintoneのアプリを使いながら、manuletで手順書を作成してみましょう。
「完璧なマニュアル」を目指す必要はありません。 最初はシンプルで構いません。少しずつ業務を型化していくことで、社内の生産性が向上し、AIを真に活用するための土台が築かれていきます。
AIは、私たちを魔法のように楽にしてくれる存在ではありません。 しかし、業務を「型化」し、情報を整理することで、AIは私たちの最高のパートナーとなってくれるでしょう。
もし「自社の業務をどうやって型化すればいいのか分からない」「kintoneとmanuletの連携についてもっと詳しく知りたい」と感じられたら、ぜひ一度ご相談ください。
業務改善は、明日からできる小さな一歩から始まります。 AI時代を生き抜くための、最初の一歩を一緒に踏み出してみませんか?
 Gibbons
Gibbons