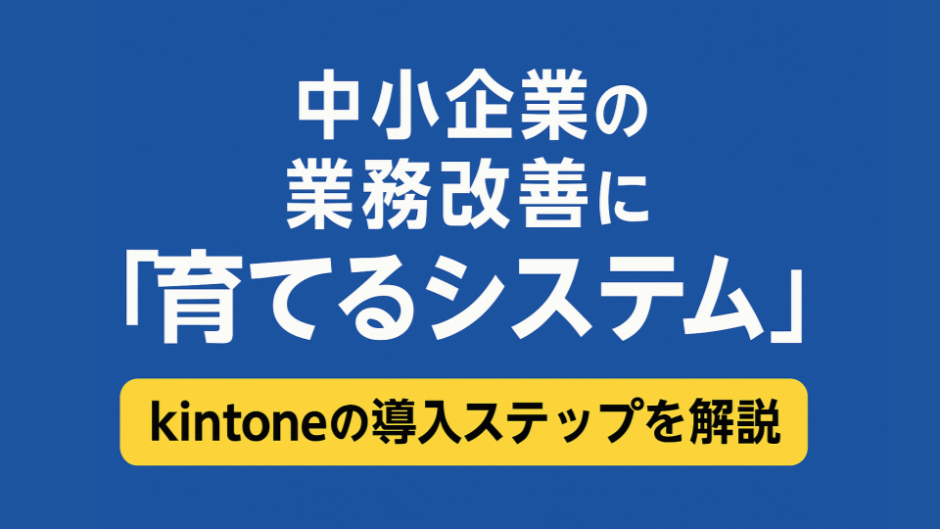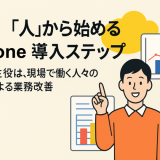「せっかくシステムを導入したのに、業務が変わると使えなくなってしまった…」
中小企業のリーダー・経営者の皆様、このような経験はありませんか?
日々変化するビジネス環境において、従来のシステムは「一度作ったら終わり」という側面が強く、業務の実態とシステムとの間にズレが生じやすいという課題がありました。その結果、本来得られるはずの業務効率化が損なわれ、「結局、手作業に戻ってしまった」というケースも少なくありません。
しかし、もしあなたの会社に、業務の変化に合わせて柔軟に「育てる」ことができるシステムがあったとしたらどうでしょうか?
今回は、私たちが数多くの中小企業様のDX推進をご支援してきた経験から、「育てるつもりで作る」kintone導入の考え方と、その具体的なステップについてお伝えします。
あなたの会社が抱える「システムと業務のズレ」という課題
中小企業の皆様が抱える「システム」に関するペインポイントは多岐にわたります。例えば、以下のようなお悩みはありませんか?
- 業務の変化に対応できない既存システム: 新しいサービスや働き方が導入されても、既存システムが対応できず、結局アナログな運用に戻ってしまう。
- 高額な改修費用と時間: システムのちょっとした変更でも、専門業者への依頼が必要で、時間も費用も膨大にかかってしまう。
- 現場にフィットしないシステム: 現場の意見が反映されにくく、使いづらいシステムを「我慢して」使っている。
- 属人化と情報共有の壁: Excelや紙での管理が中心で、情報が分散し、必要な情報が見つからない、共有しにくい。
これらの課題は、日々の業務効率を低下させるだけでなく、従業員のモチベーション低下や、ひいては企業の成長を阻害する要因にもなりかねません。
kintoneが解決する「業務に寄り添うシステム」という新しいカタチ
私たちが強くおすすめするkintoneは、これらの課題を根本から解決する可能性を秘めたツールです。従来のシステムとkintoneの最も大きな違い、それは「運用しながらでも改善が進められる」という点にあります。
従来のシステムが「完成形」を目指すものだとすれば、kintoneは「成長する生命体」のようなものです。
業務フローや組織体制に変更があった際、従来のシステムではその変更に追従することが難しく、結果として「運用でカバーする」という状況が生まれ、せっかくの効率化が損なわれることがありました。
しかしkintoneは、当初の想定に変更があった時点で、システム側を比較的容易に修正・調整できるのです。もちろん慎重に行う必要はありますが、従来のシステム開発と比較して、圧倒的に短期間かつ低予算で修正が可能です。
これにより、システムが業務に常に寄り添い、変化の激しい現代において「使えないシステム」になることを防ぎます。
「育てる」ためのkintone導入、実践ステップ
では、具体的にどのようにkintoneを導入し、「育てて」いけばよいのでしょうか。中小企業の皆様が実践しやすい導入ステップをご紹介します。
ステップ1:課題の明確化と「小さく始める」意識
まず、自社の「業務の滞り」や「非効率な部分」を具体的に洗い出しましょう。そして、全ての課題を一気に解決しようとせず、最も喫緊性の高い課題から「小さく始める」ことが成功の鍵です。
例えば、「営業日報の作成・集計に時間がかかっている」「顧客情報がバラバラに管理されている」といった具体的な課題を特定します。そして、その課題を解決するための最小限のkintoneアプリ(データベースのようなもの)を設計します。
ステップ2:現場を巻き込む「共創型」のシステム構築
kintoneは、ITの専門知識がなくても、現場の担当者が自らアプリを作成・改善できるのが大きな特長です。
実際にシステムを使う現場の声を吸い上げ、彼らが「こうしたい」と思う形を一緒に考えていくことで、使いやすく、業務にフィットしたシステムが生まれます。最初から完璧を目指さず、試行錯誤しながら、少しずつ改善していくプロセスを重視してください。
例えば、営業日報アプリであれば、「どんな項目が必要か」「入力は楽か」「集計はしやすいか」といった点を、実際に日報を書く営業担当者と一緒に検討し、形にしていきます。
ステップ3:スモールスタートからの「改善と拡張」
最初のアプリが完成したら、まずは実際に運用を開始してみましょう。そして、使っていく中で「もっとこうしたら便利になる」「この機能を追加したい」といった声が必ず出てきます。
kintoneは、これらの声をすぐにシステムに反映させることができます。例えば、日報アプリに「今日の訪問先の課題」という項目を追加したり、営業成績を自動でグラフ化する機能を追加したり、といった改善を、自社内で行うことが可能です。
このように、「作って終わり」ではなく、「使って改善し、さらに良くしていく」というサイクルを回すことで、システムは業務と共に成長していきます。
ステップ4:成功体験の共有と全社展開
最初に導入したkintoneアプリで効果が出始めたら、その成功体験を社内で積極的に共有しましょう。成功事例を具体的に伝えることで、他の部署や業務への横展開がスムーズになります。
「営業日報が効率化されて、集計時間が半分になった」「顧客対応の履歴が一元化されて、情報共有がスムーズになった」といった具体的な効果を共有することで、社内全体のDXへの意識が高まります。
kintone導入で得られる具体的なビジネス効果
「育てる」kintone導入によって、あなたの会社は以下のような具体的なビジネス効果を享受できます。
- 業務効率の大幅向上: 従来手作業で行っていた業務がシステム化され、時間とコストを削減できます。例えば、営業日報の集計時間が月間〇時間削減、見積作成時間が△%短縮といった具体的な効果が見込めます。
- 変化への迅速な対応: 事業環境の変化や新しい業務フローの導入に、システムが柔軟に対応できます。これにより、ビジネスチャンスを逃さず、競争優位性を確立できます。
- データに基づいた意思決定: 業務データがkintoneに蓄積されることで、現状を正確に把握し、データに基づいた経営判断が可能になります。例えば、顧客ごとの売上推移を分析し、最適な営業戦略を立案できます。
- 情報共有とコラボレーションの促進: 情報が集中管理されることで、部門間の連携がスムーズになり、チーム全体の生産性が向上します。
- 従業員のエンゲージメント向上: 現場の意見が反映されやすいシステムは、従業員のストレスを軽減し、業務へのモチベーションを高めます。
よくある障壁と克服法:「アイディア」と「工夫」が鍵
kintone導入において、いくつか障壁となる点もありますが、これらは「アイディア」と「工夫」で乗り越えられます。
- IT人材不足: 専門のIT担当者がいなくても、kintoneはノーコード・ローコードツールであるため、現場の業務を理解している担当者が自らアプリを作成・改善できます。必要に応じて、外部の専門家からの初期支援を活用することも有効です。
- 「今までのやり方を変えたくない」という抵抗: まずは一部の部署や業務からスモールスタートし、成功事例を作ることで、徐々に周りを巻き込んでいくことが重要です。また、システム導入の目的(なぜ変えるのか、変えるとどう良くなるのか)を丁寧に説明し、理解を得る努力も不可欠です。
- 「何から手をつけて良いかわからない」: 漠然と「業務効率化」と考えるのではなく、「営業日報の作成をもっと楽にしたい」「顧客情報を一元管理したい」など、具体的な課題に絞って取り組むことが大切です。まずは一つの小さな課題から、アイディアを形にしてみましょう。
これらの障壁を乗り越えるためには、**「視点を変える」**ことが重要です。既存のやり方にとらわれず、どうすればもっと効率的に、もっとスムーズに業務が進むかを、自由に発想してみましょう。
次のステップ:あなたの会社で「育てるシステム」を始めませんか?
kintoneは、ただの業務システムではありません。それは、あなたの会社の業務と共に成長し、変化に強く、未来を切り拓くための「パートナー」になり得るものです。
「育てるつもりで作る」という考え方は、決して難しいことではありません。大切なのは、完璧を目指すのではなく、現場の声を大切にし、少しずつ改善を重ねていく姿勢です。
もし今、あなたの会社が業務効率化やDX推進に課題を感じているのであれば、ぜひkintoneの導入をご検討ください。
最初は小さな一歩かもしれませんが、その一歩が、あなたの会社の未来を大きく変えるきっかけとなるはずです。
業務改善の「アイディア」と「工夫」を形に
私たちは、数多くの中小企業様のkintone導入をご支援してまいりました。それぞれの会社が抱える独自の課題に対し、共に「アイディア」を出し、様々な「工夫」を凝らしてkintoneを「育てて」きました。
「こんなことできるかな?」「うちの会社には合わないのでは?」といったご心配は無用です。まずは、あなたの会社が抱える「業務のモヤモヤ」を私たちにお聞かせください。私たちが培ってきた経験と知識で、最適な解決策を共に探し、あなたの会社の「業務改善」を全力でサポートいたします。
さあ、あなたの会社も、業務に寄り添う「育てるシステム」を始めてみませんか?
 Gibbons
Gibbons