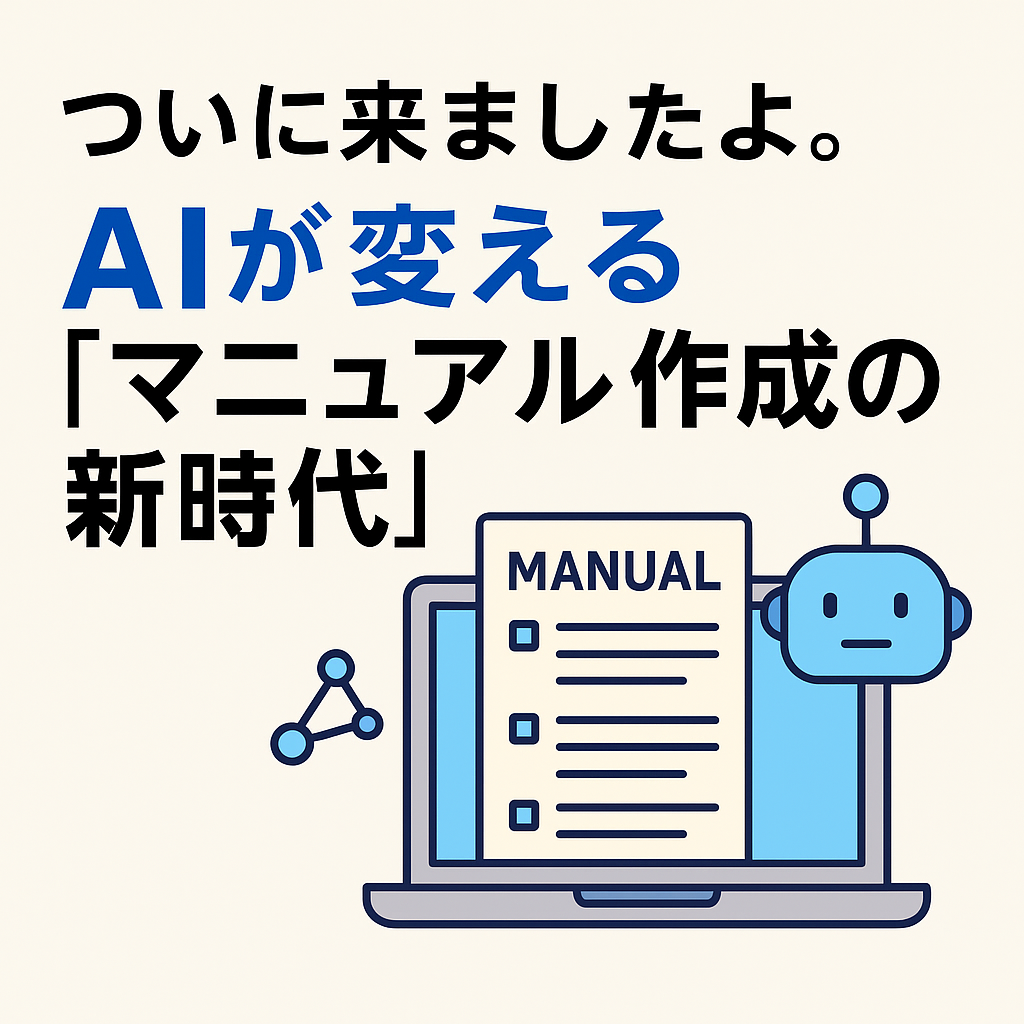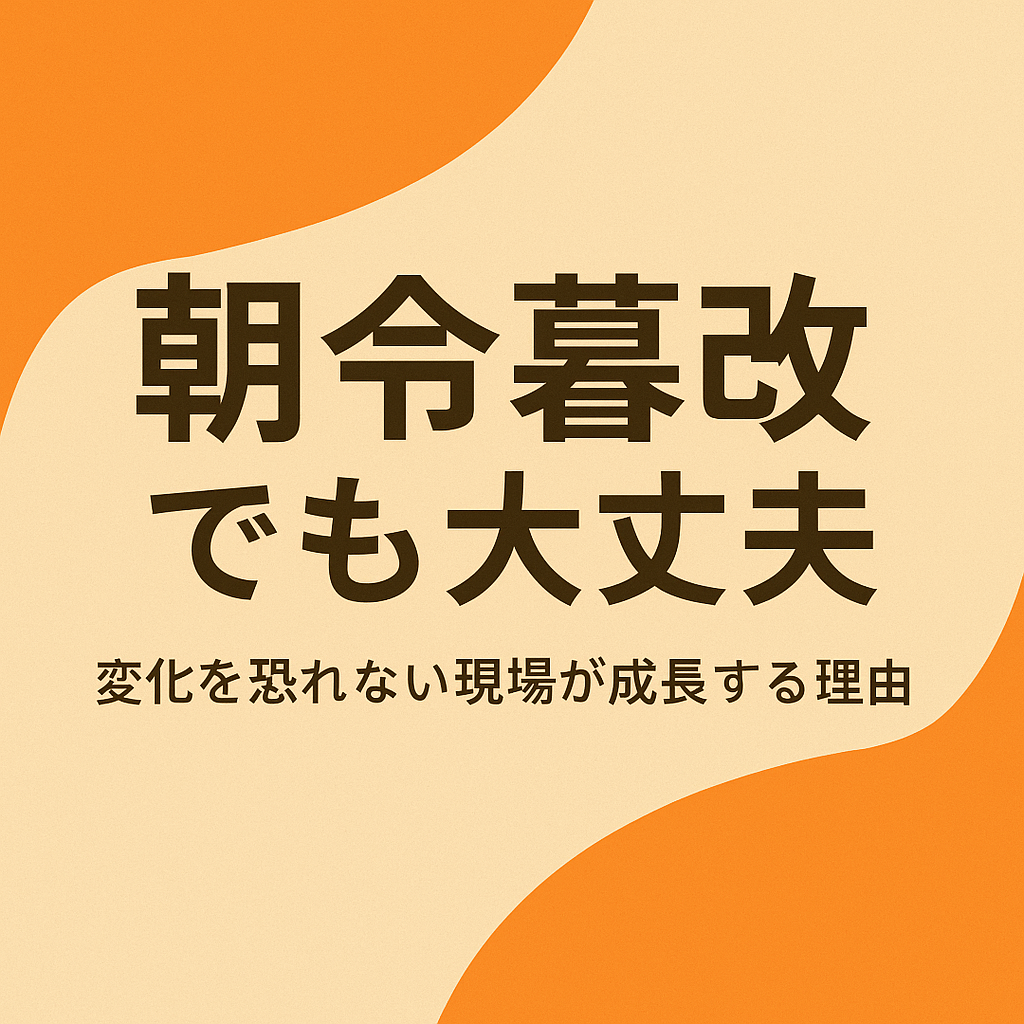「マニュアルを作らなきゃ」と思いながらも、日々の業務に追われて後回しになっていませんか?
そんな方に、少し希望の話を。ついに“マニュアル作成の壁”を乗り越える時代がやってきました。
マニュアル作成が進まない本当の理由
どの企業でも、「マニュアルを整備しよう」という声は上がります。
しかし、実際に形にできている企業は意外と少ないものです。
理由は単純で、「時間がない」「どこから書けばいいかわからない」の二つに尽きます。
業務の中で誰かがやってくれていること、口頭で済ませていることを、文章に落とし込むには労力が必要です。
それに、「完璧な形にしよう」と思うほど、手が止まってしまいます。
実はこの“最初の1枚目を作る”ところに、多くの企業がつまずいています。
生成AIは「マニュアル作成の壁」を壊す
ここで注目したいのが、生成AI(Generative AI)の活用です。
最近は「AIが文章を作る」ことが当たり前になりつつありますが、マニュアル作成との相性は抜群です。
たとえば、AIに次のような指示(プロンプト)を出すとします。
「新人スタッフ向けに、顧客対応の基本ルールをまとめてください」
するとAIは、わずか数秒で大枠を整えた文章を提示してくれます。
7割くらいの内容がすでに形になっている感覚です。
残りの3割は、実際の現場や自社ルールに合わせて修正すればOK。
つまり、AIが“たたき台”を作り、人が“現場のリアリティ”を加える。
この流れを取り入れるだけで、マニュアル作成のハードルはぐっと下がります。
AIに任せるための「上手な指示」の出し方
AIをうまく活用するには、「何を伝えるか」が鍵になります。
曖昧な指示よりも、次のように具体的な情報を渡すのがおすすめです。
- 対象者:新入社員向け or ベテラン社員向け
- 内容の目的:教育、引き継ぎ、品質維持など
- トーン:やさしく説明する、手順を箇条書きに、など
例として、次のようなプロンプトが使えます。
「新入社員が初めて顧客対応を行う際の手順を、やさしい言葉で5つのステップにまとめてください。」
このようにAIに「誰に」「どんな目的で」使うマニュアルなのかを明確に伝えることで、
実際の現場で使える内容が出力されやすくなります。
AIは魔法ではありませんが、正しい指示を出せば非常に頼れる相棒になります。
新人教育の効率が変わる
マニュアルが整備されると、新人教育の時間が劇的に減ります。
教える人が毎回同じ説明をする必要がなくなり、
新人も「自分で確認できる安心感」を持って成長できます。
AIを使えば、業務内容の更新も素早く行えます。
「手順が変わったけど、マニュアルの修正が追いつかない」という課題も、
AIがあれば簡単にアップデートできる時代になっています。
たとえば、次のように依頼できます。
「既存マニュアルの“お客様への電話対応手順”を、2025年版に更新してください。」
こうした“部分更新”もAIは得意です。
マニュアルを「作る」から「育てる」へ。
そんな意識の変化が、企業の教育力を底上げしていきます。
マニュアルを現場に「根付かせる」ために
せっかく作ったマニュアルも、現場で使われなければ意味がありません。
重要なのは、「どこで」「どうやって」使われるかを意識することです。
- 業務アプリやツールの中で閲覧できるようにする
- 作業手順の近くにリンクを置く
- スマホやタブレットからも見やすい形式にする
特に、現場で動くスタッフや新人が「すぐ見られる」仕組みを整えることがポイントです。
マニュアルは“探すもの”ではなく、“使うもの”。
この発想を持つだけで、日々の業務がぐっとスムーズになります。
今こそ“共有の仕組み”を整えるチャンス
AIの登場によって、マニュアル作成のハードルは確実に下がりました。
でも、それ以上に大事なのは「共有の仕組み」を作ることです。
知識やノウハウは、人の頭の中だけにあると消えてしまいます。
一方で、マニュアルとして残しておけば、誰かの次の一歩を支える資産になります。
AIを上手に使いながら、業務を可視化し、学びを共有する文化を育てていきましょう。
それが、これからの中小企業が強くなるための第一歩です。
マニュアルは、単なる「手順書」ではなく「知識をつなぐ仕組み」です。
AIを活用して“最初の一歩”を作り、現場で育てていく。
そんな時代の流れを、今こそ取り入れてみませんか。
 Gibbons
Gibbons