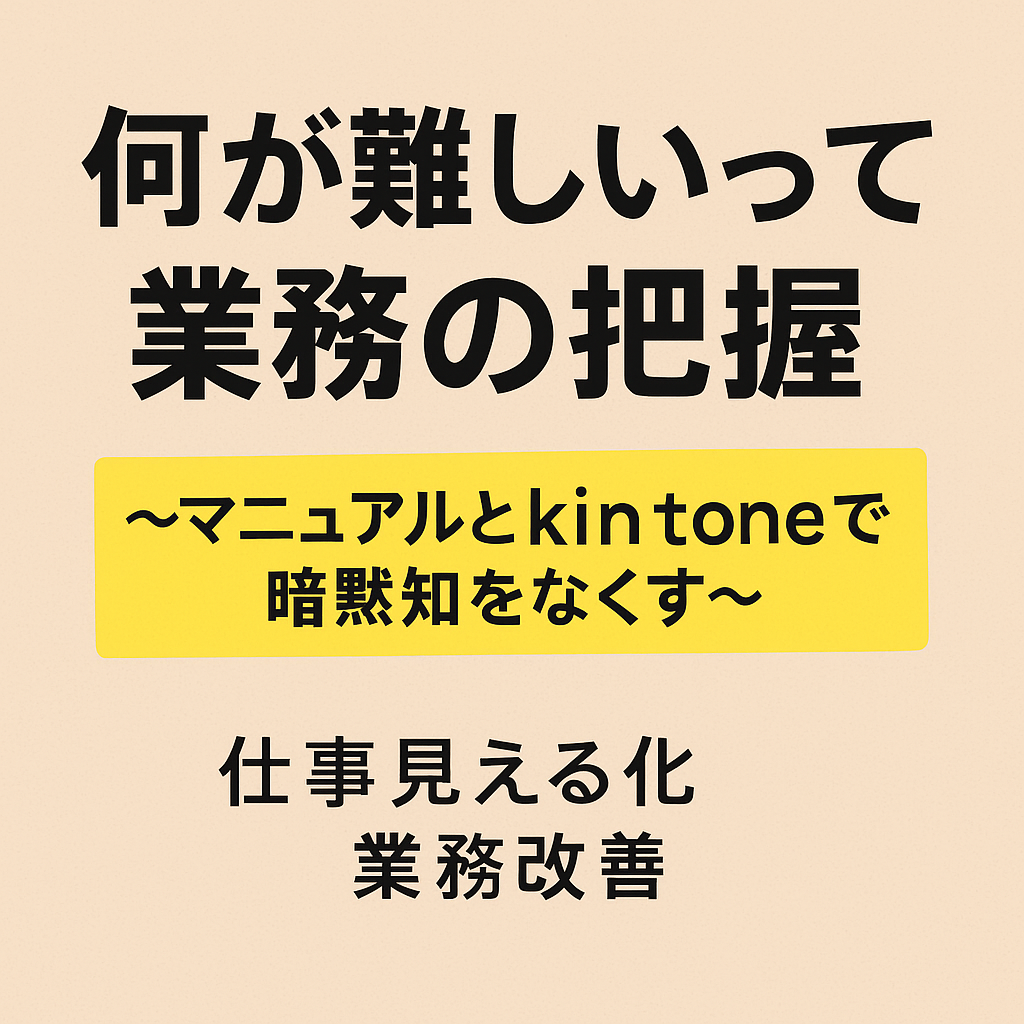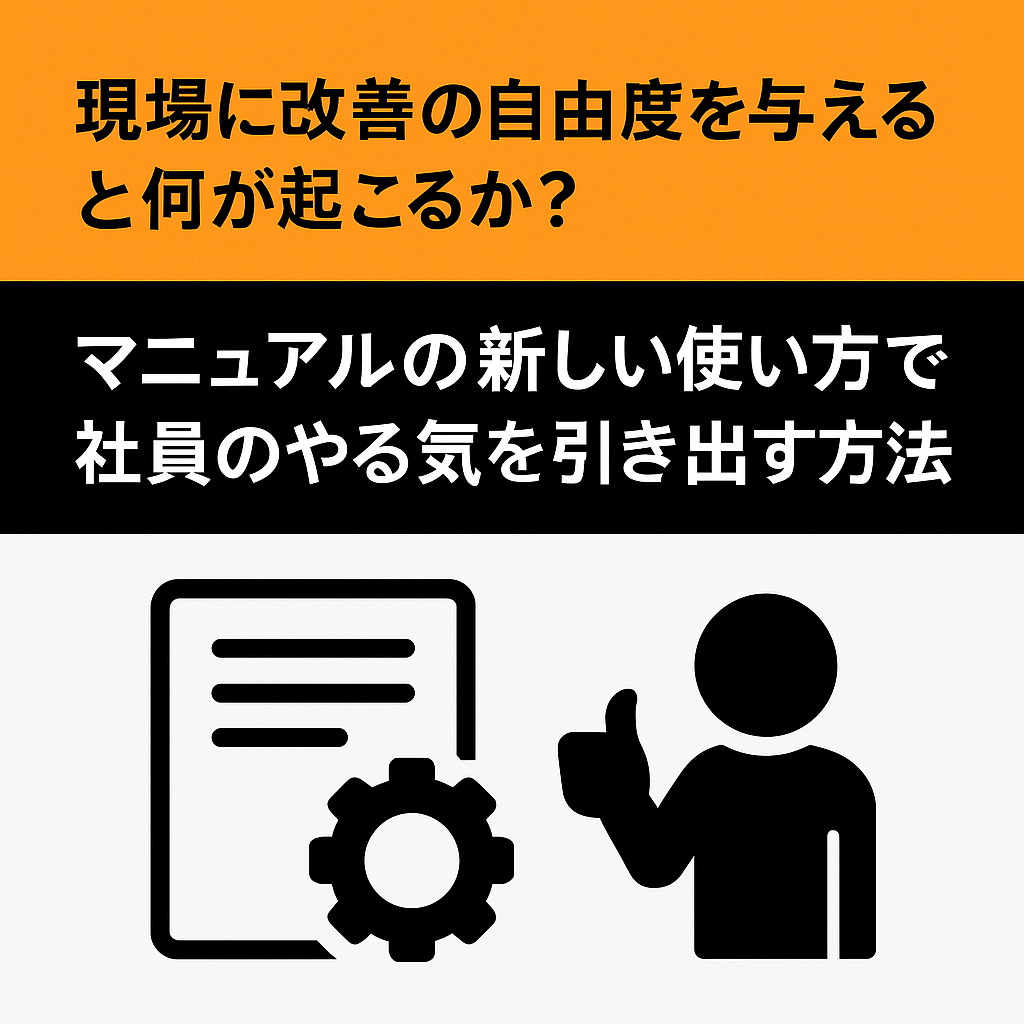〜マニュアルとkintoneで暗黙知をなくす〜
「業務の把握」が一番難しい理由
中小企業の経営者やリーダーにとって、「業務改善」や「DX推進」という言葉はもはや避けて通れません。しかし、実際に現場を支援していて強く感じるのは、業務の把握そのものが一番難しいという現実です。
日常的に行われている仕事は、あまりにも当たり前になっているために言語化されにくい。例えば、ベテラン社員が無意識のうちに処理している作業や、お客様とのちょっとしたやりとりの中で発生する判断。これらは「暗黙知」となり、なかなか外からは見えません。
その結果、
- 新入社員が同じ作業を再現できない
- 属人化が進み、休暇や退職で業務が滞る
- 改善の出発点がつかめない
といった問題が生まれてしまいます。
マニュアルは「縛り」ではなく「共通言語」
「マニュアル」という言葉には、どうしても「縛り」「工夫を奪う」といったネガティブなイメージがつきまといます。ですが本来のマニュアルは、業務を見える化し、共通の土台を作るための道具です。
マニュアルが整っている企業ほど、社員同士の会話がスムーズで、改善の議論が建設的に進みます。つまりマニュアルは、組織における「共通言語」のような役割を果たしているのです。
さらにAI時代の今だからこそ、マニュアルの価値は高まっています。生成AIは提案や文章化を助けてくれますが、その前提となる「業務の型」が曖昧では効果を発揮できません。マニュアルを整備しておくことで、AIもより精度高く支援できるのです。
kintoneで「業務の把握」を進める
そこで力を発揮するのが、kintoneのようなローコードツールです。
Excelや紙での記録は、情報が散らばりやすく、更新が止まりがちです。一方kintoneでアプリ化すれば、入力や参照が日常の業務フローに組み込まれるため、業務の実態が自然と見える化されていきます。
- 顧客対応の履歴
- 日報や作業記録
- 在庫や発注の流れ
こうした情報がkintoneに集まることで、業務の全体像が徐々に浮かび上がってきます。さらに、その過程で「普段は無意識にやっていた作業」が表に出てくるのです。
Manuletで「マニュアル」と「現場」をつなぐ
ただ、情報をアプリに記録しただけでは十分ではありません。それをどう使うか、どう共有するかが重要です。そこで役立つのが、kintone上でマニュアルを表現できるツール「manulet」です。
manuletを活用すると、
- 作業手順を画像付きで直感的に記録
- ナレッジやQ&Aを現場にすぐ反映
- スマホやタブレットからも確認可能
といった仕組みを、シンプルに実現できます。つまり「現場で生まれた情報」と「業務マニュアル」を同じ基盤で扱えるようになるのです。これにより、業務の把握 → マニュアル化 → 改善という流れが途切れず回り始めます。
暗黙知をなくすことが業務改善の第一歩
業務改善に取り組む際、「何から始めればいいのか」と悩む企業は少なくありません。ですが答えはシンプルで、まずは暗黙知をなくすこと、属人化を防ぐことです。
- 普段の作業を言語化してみる
- 簡単なチェックリストにまとめてみる
- kintoneで業務をアプリ化してみる
- マニュアルを見やすく整えてみる
この小さな一歩が、やがて大きな改善サイクルにつながります。
まずは「表現すること」から
「何が難しいって業務の把握」。これは多くの中小企業に共通する悩みです。しかし、表現しなければ見えないものも、ツールを活用すれば形にできます。
マニュアルやkintone、そしてmanuletのような仕組みを使うことで、
- 暗黙知をなくす
- 業務を見える化する
- 改善のサイクルを回す
ことが可能になります。
今日からできるアクションとして、まずは社内の一つの業務を取り上げて、手順を「書いてみる」「kintoneに入力してみる」といった小さな試みを始めてみてください。その積み重ねが、将来の大きな効率化と成長につながっていきます。
 Gibbons
Gibbons