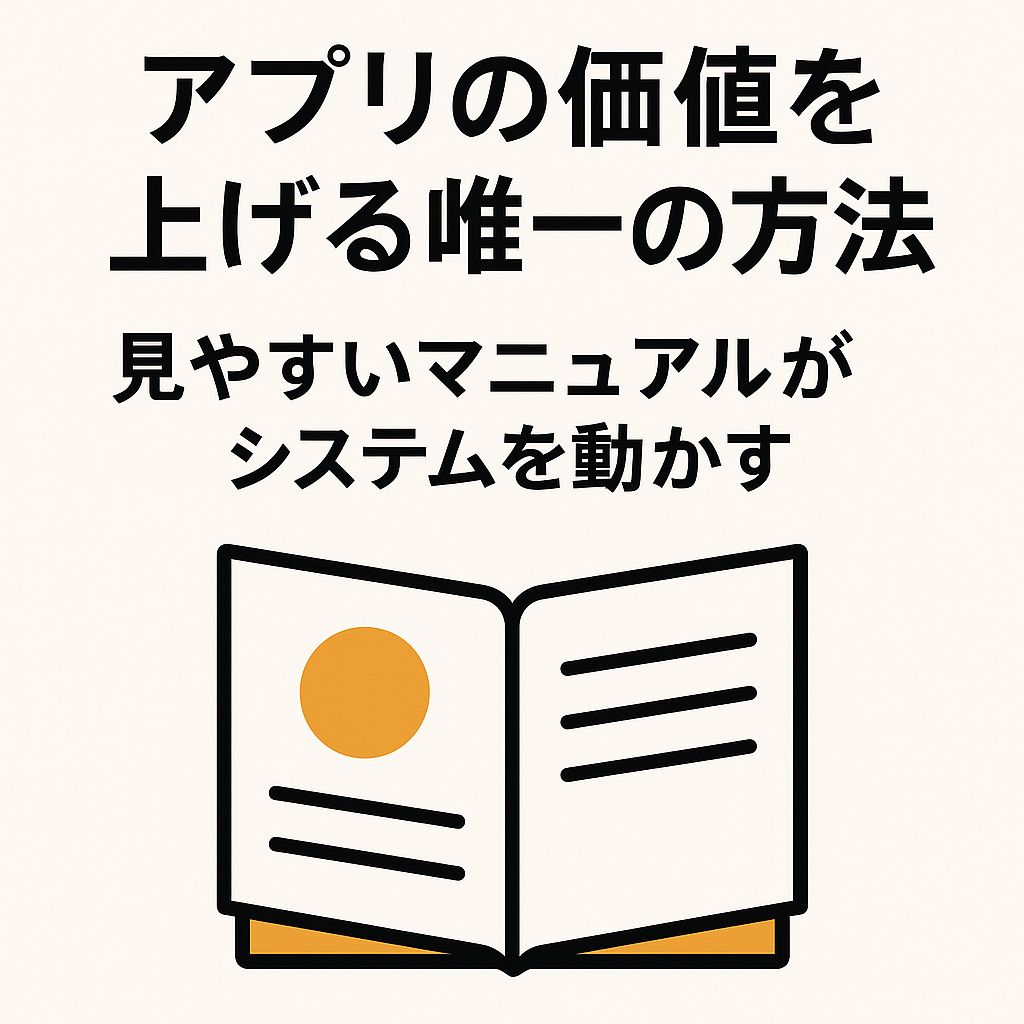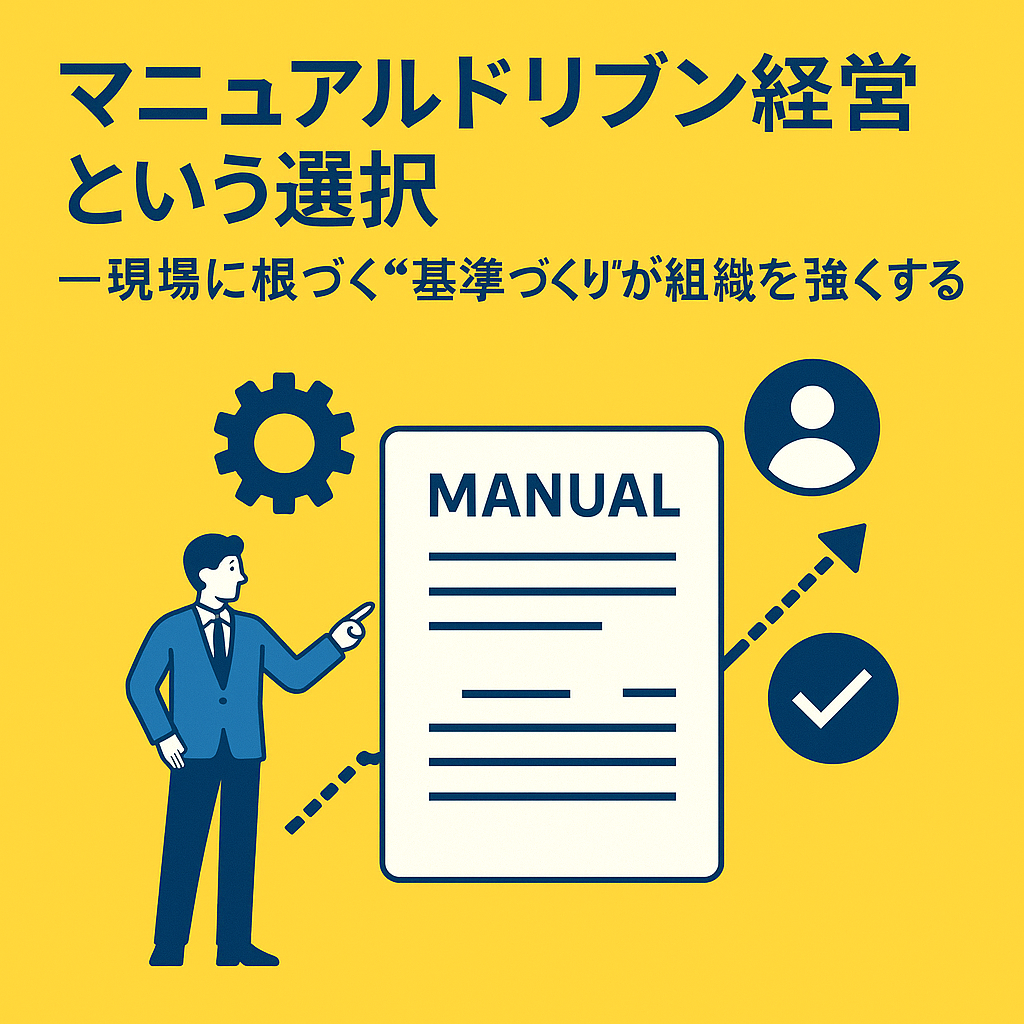せっかく時間をかけて作ったkintoneアプリや新しい仕組み。完成したときは満足しても、いざ現場に渡してみると「使われない」「よく分からない」と言われた経験はありませんか?
実は、アプリの価値を決めるのは「機能」よりも「伝え方」。その鍵となるのが“見やすいマニュアル”です。
■ アプリが「動かない」本当の理由
kintoneやノーコードツールで作られたアプリは、業務効率化の大きな力を秘めています。
しかし、どれだけ便利な機能を盛り込んでも、「現場で使われない」まま終わるケースが少なくありません。
原因は単純です。作った人と使う人の“理解のギャップ”が埋まっていないからです。
作成者は「誰でも分かるように作ったつもり」でも、利用者からすると「どこを押せばいいのか分からない」「入力項目が多くて不安」と感じてしまう。
その結果、せっかくのアプリが放置され、「やっぱり紙のほうが早い」と逆戻りしてしまうのです。
■ 「伝える設計」こそがアプリ価値を決める
システム開発というと、つい機能面やデザインに目が行きがちです。
けれども本当に大切なのは、「どうすれば使い手が迷わず使えるか」という設計です。
ここで効果を発揮するのが、見やすく整理されたマニュアル。
導線の説明、操作例、注意点を短い文章と画像で示すだけで、利用者の不安はぐっと減ります。
マニュアルがあることで、
- 「どこに何を入力すればいいか」が一目で分かる
- 新人や異動者も同じ手順で作業できる
- トラブル発生時に自力で解決できる
といった“自走できる現場”が生まれます。
つまり、マニュアルは「説明書」ではなく、システムの一部なのです。
■ 「使える仕組み」を渡す、という発想
ベンダーやシステム担当者の中には、「アプリを作ること」がゴールになっているケースがあります。
しかし、本当のゴールは「現場が使いこなせるようになること」。
たとえばkintoneのアプリを納品する際、操作手順をまとめた簡単なマニュアルを一緒に添えるだけで、導入後の定着率は格段に上がります。
そのマニュアルを共有フォルダに入れておくだけでなく、アプリの中に埋め込むことで、ユーザーが迷ったときにすぐ確認できるようになります。
もしあなたが開発側であれば、
「アプリの完成=納品」ではなく、「活用までが設計」
と考えるだけで、プロジェクトの評価は大きく変わるでしょう。
■ 現場に渡す「プレゼント」としてのマニュアル
「マニュアル」というと、つい「作らなきゃいけない面倒なもの」と思われがちです。
ですが、それを“プレゼント”と考えてみるとどうでしょう。
- 使う人が安心できる
- 操作がスムーズに進む
- チームの共通理解が生まれる
そんな贈り物のようなマニュアルを添えることで、アプリの印象は一変します。
同じ仕組みでも、「丁寧に説明してくれている」と感じるだけでユーザーの信頼が増し、結果としてアプリ自体の価値も高まるのです。
■ 使われ続けるアプリにするための3ステップ
- 利用者目線で“つまづきポイント”を洗い出す
現場の人にヒアリングし、「ここが分かりづらい」という声を拾う。 - 短く・見やすくまとめる
説明は一文一意。箇条書きや画像を活用して、「考えなくても分かる」構成に。 - アプリ内やkintone上に配置する
いつでも見られる場所に置くことで、“参照されるマニュアル”になります。
これだけで、アプリは「止まる仕組み」から「動き続ける仕組み」へと変わります。
アプリやシステムの価値は、機能の多さではなく「どれだけ使われるか」で決まります。
その第一歩は、現場に“見やすいマニュアル”を贈ること。
小さな工夫が、アプリを「生きた仕組み」へと変えていきます。
 Gibbons
Gibbons