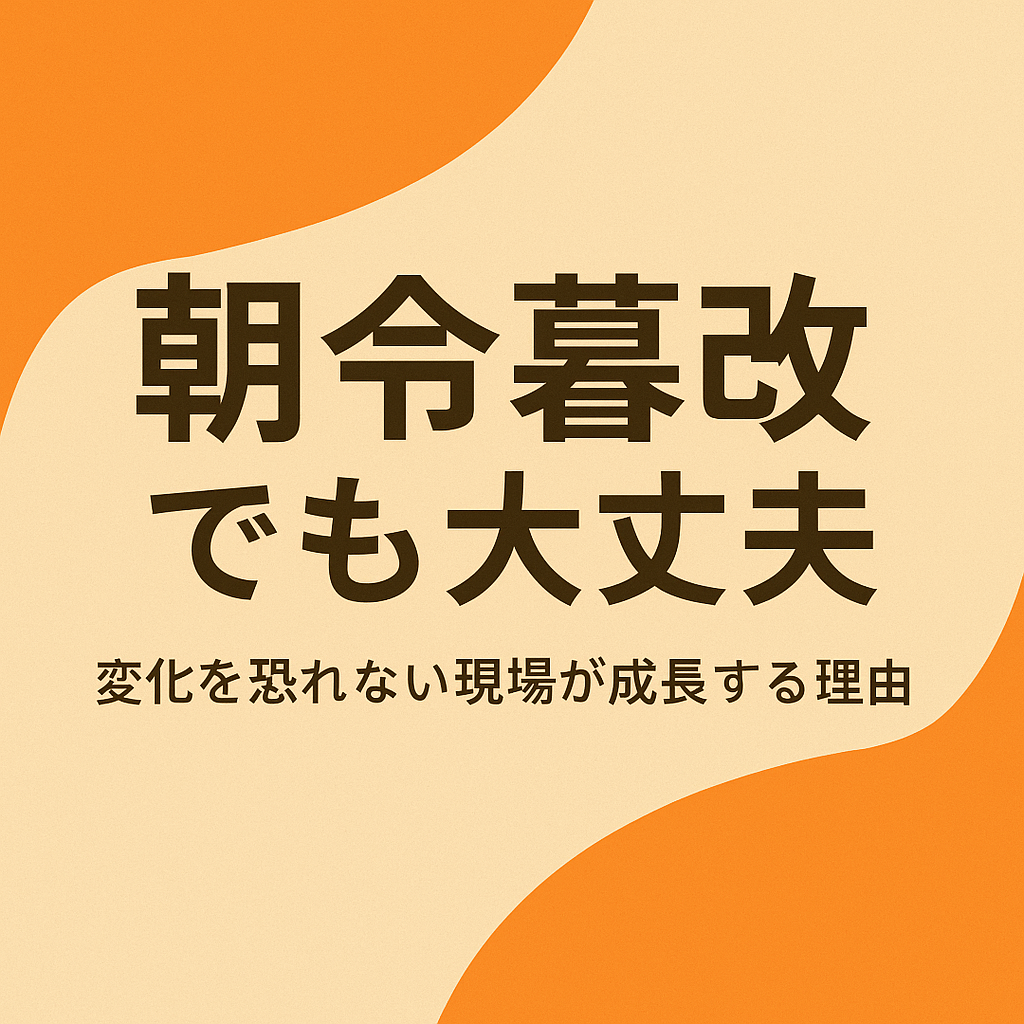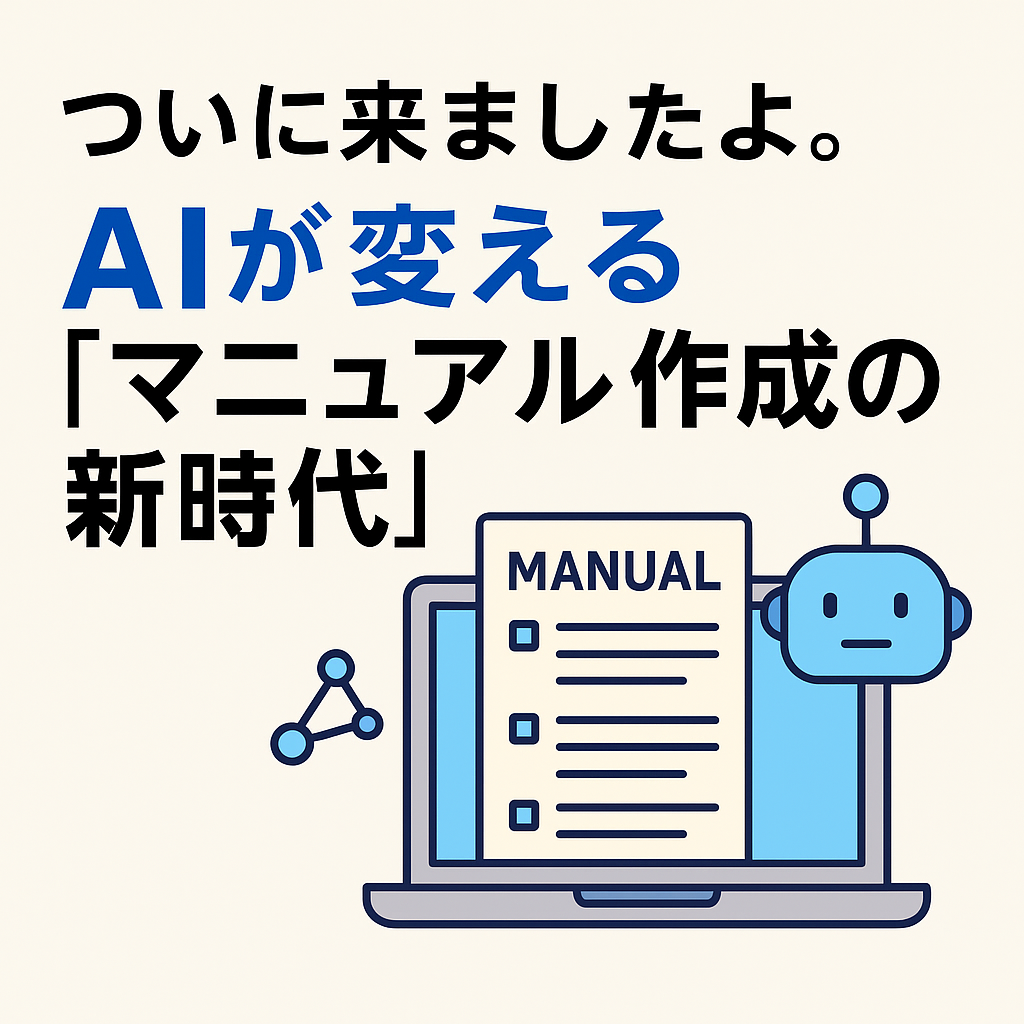「朝令暮改」という言葉には、コロコロ方針が変わる悪い印象がつきものです。ですが、変化のスピードが速い今の時代、朝令暮改こそ現場を強くする力になるかもしれません。大切なのは、混乱を恐れず柔軟に改善を重ねる「しくみ」を持つことです。
現場で起きている「挑戦」と「戸惑い」
先日、ある飲食チェーンの店舗を訪れた時のこと。
そのお店では、店舗独自の新メニューを試験的に提供していました。挑戦的で面白い取り組みです。
しかし、実際に現場を見てみると、オーダーがうまく通らなかったり、提供の順番がずれたりと、少し混乱が見られました。スタッフ同士も「次どうする?」と戸惑い気味。
でも私はその光景を見て「これは失敗じゃない」と感じたのです。むしろ「変化の現場」こそ成長のチャンス。問題は「次にどう改善するか」なのです。
スピード改善のカギは「共有」と「更新」
朝に立てた方針が夕方には変わる。
それを悪いことではなく、「現場の柔軟性」として活かせたらどうでしょうか。
デジタルツールを使って情報を記録・共有しておけば、「何をどう変えたのか」「次にどう対応するのか」を素早く全員で確認できます。
例えば、営業終了後に「今日のオペレーション、ここを直そう」という話が出たとき、
・すぐに手順を更新できる
・スタッフ全員が同じ内容を確認できる
・翌日の朝から改善を実行できる
という流れが作れます。
この“スピード感あるPDCA”が、変化に強い現場づくりの鍵になります。
アナログでは追いつけない「変化のスピード」
紙のマニュアルや共有フォルダの文書では、更新に時間がかかりすぎます。
現場で改善案が出ても、翌日には忘れてしまったり、反映されないままになったり。
せっかくの「気づき」が埋もれてしまうのはもったいないことです。
デジタルマニュアルなら、現場で気づいたその瞬間に更新できます。
しかも、スマートフォンやタブレットから誰でも閲覧できるので、「あのページ直した?」と確認する必要もありません。
変化をチャンスに変えるスピードは、ツールの使い方で決まります。
「朝令暮改」をポジティブにとらえる文化を
重要なのは、「方針変更=混乱」ではなく、「柔軟な改善=進化」と捉える文化を育てることです。
現場で起きる小さなトラブルや試行錯誤は、すべて組織の学びにつながります。
「昨日より少し良くなった」を積み重ねるために、情報をオープンにし、誰でも改善提案できる環境を整えましょう。
「どうせまた変わる」と言われる職場から、
「どんどん良くなるね」と言われる職場へ。
その違いを生むのは、スピードと共有の意識です。
現場の声を次の改善へ
夕方、スタッフに「今日どうだった?」と声をかけてみてください。
その一言から、次の改善のヒントが見つかるかもしれません。
そして、その気づきをチーム全員がすぐに共有できる仕組みを持つこと。
それが「朝令暮改でも大丈夫」な現場をつくります。
変化を恐れず、スピード感をもって改善を重ねること。
そのための基盤に「共有できるマニュアル」があります。
今日の気づきを明日の行動につなげる。
それが、現場が成長し続ける一番の近道です。
 Gibbons
Gibbons